簡易課税制度の概要と改正経緯
簡易課税制度は、消費税制度の導入時に、すべての課税事業者に一律に本則課税による仕入控除税額の算定を求めることは困難であることから、中小事業者の事務処理能力を勘案して設けられた制度です。
また、その採用の際の説明としては「多段階にわたり課税し、税の累積排除のための前段階控除方式をとる消費税は、我が国の企業にとってなじみの薄いものであるため、事業者の事務負担に配慮した措置が種々講じられていますが、特に中小事業者の事務負担を考慮して、この簡易課税制度が設けられ、売上に係る消費税額を基礎として、簡単に仕入に係る消費税額を計算することができる」こととされました。
制定時の簡易課税制度は、その基準期間における課税売上高が5億円以下である課税期間について、納税地所轄の税務署長に届出書を提出した場合に適用され、また、仕入れに係る消費税額は、売上に係る消費税額に主たる事業に係るみなし仕入率(原則80%、卸売業者90%)を乗じて計算するというものでした。
しかし、適用上限が5億円ということについては、特例措置であるにも関わらず、適用事業者が多すぎるのではないかという問題が指摘されていた。実際のデータからも、簡易課税の適用事業者の中にも本則計算を行なっている事業者が相当程度存在すること、売上規模が5億円程度の事業者の場合、相当数の従業員数及び経理担当者がいるということが明らかになっていた。また、みなし仕入率についても、業種によっては実際の仕入率とみなし仕入率との間に乖離が大きいことから、速やかにこれを是正し、制度の公平性を高めるべきとの指摘されました。
このような指摘を受け、平成3年の消費税法の改正においては、適用限度額が5億円から4億円に引き下げられるとともに、みなし仕入率について、実態により適合させるために、それまでの卸売業者とその他という2事業区分から、4事業区分(卸売業90%、小売業80%、製造業等70%、その他の事業60%)に細分化されました。
その後の平成6年の消費税法の改正(平成9年4月施行)では、特例措置であるにも関わらず、課税事業者の6割が簡易課税制度を選択していると見込まれることや、事業規模の大きい事務処理能力を充分に備えた事業者が、結果的に本則課税と比べて有利か不利かといった判断の下に簡易課税制度を選択している可能性が高いということ等を踏まえ、適用上限額を4億円から2億円に引き下げ、平成8年度税制改正(平成9年4月施行)においては平成8年政令86号によって、みなし仕入率について、第4種事業区分のうち、不動産業、運輸通信業及びサービス業を第5種事業区分とし、そのみなし仕入率を50%と定めました。
さらに、平成15年度税制改正においては、事業者免税点制度の改正に伴って新たに課税事業者となった事業者の事務負担に配慮しながらも、より公平で透明性のある制度にするため、適用上限額が2億円から5,000万円に引き下げられた。その後、平成22年度の税制改正において、課税事業者選択制度の取り止めを3年間制限する特例及び資本金1,000万円以上の新設法人に対して事業者免税点制度を3年間不適用とする特例を設ける改正が行われたのに併せて、これらの適用を受ける課税期間中は簡易課税制度の適用も受けられないとする改正が行われ、平成26年度の税制改正において新たに第6種の区分が設けられ現在に至ります。簡易課税制度の改正経緯の概要について、次表のようになります。
| 簡易課税制度の改正概要 | ||||
| 改正(制定)年 | 施行年月日 | 適用対象事業者 | 業種区分 | みなし仕入れ率 |
| 昭和63年 (制定年) |
平成元年4月1日 | 課税売上高が5億円以下の事業者 (免税事業者を除く) |
卸売業 | 90% |
| 卸売業以外の事業 | 80% | |||
| 平成3年 | 平成3年10月1日 | 課税売上高が4億円以下の事業者 (免税事業者を除く) |
卸売業 | 90% |
| 小売業 | 80% | |||
| 製造業等 | 70% | |||
| その他の事業 | 60% | |||
| 平成6年 平成8年 |
平成9年4月1日 | 課税売上高が2億円以下の事業者 (免税事業者を除く) |
卸売業 | 90% |
| 小売業 | 80% | |||
| 製造業等 | 70% | |||
| 飲食店業等 | 60% | |||
| サービス業等 | 50% | |||
| 平成15年 | 平成16年4月1日 | 課税売上高が5,000万円以下の事業者 (免税事業者を除く) |
卸売業 | 90% |
| 小売業 | 80% | |||
| 製造業等 | 70% | |||
| 飲食店業等 | 60% | |||
| サービス業等 | 50% | |||
| 平成26年 | 平成26年4月1日 | 課税売上高が5,000万円以下の事業者 (免税事業者を除く |
卸売業等 | 90% |
| 小売業等 | 80% | |||
| 製造業等 | 70% | |||
| 飲食業等 | 60% | |||
| サ-ビス業等 | 50% | |||
| 不動産賃貸業等 | 40% | |||
簡易課税制度に対する税制調査会の考え方
簡易課税制度について税制調査会は、税制調査会実施状況フォローアップ小委員会報告(平成2年10月30日総会提出)において、「この制度が特例措置であるにもかかわらず、あまりにも多くの事業者が簡易課税を選択できることとなっているのは問題ではないかという指摘がなされている」とし、「基本的には、制度の定着や納税事務の習熟の度合いに応じて、できるだけ多くの事業者に対して本則計算を求めていくことが本来の姿であると考えられる」として、あくまでも簡易課税は特例であるという点を強調した上で、中小事業者に対して、簡素な税額計算の仕組みを設けること自体には一定の合理性を認めつつも、制度の適用範囲の縮小と、制度自体の公平性確保のためのみなし仕入率の適用区分や水準についても実態に即したものにしていく必要性を指摘しています。
平成6年の消費税法の改正の前年である平成5年11月の今後の税制のあり方についての答申においても、できるだけ多くの事業者に対して本則計算を求めていくことが本来の姿であるとし、「引下げによって影響を受ける中小事業者の事務負担に配慮しながら簡易課税制度の適用上限を更に引き下げていく方向で検討を行うことが適当である」とした。また、みなし仕入率については、適用区分の更なる細分化を行うべきとの意見の一方で、適用区分の「更なる細分化が、制度の複雑化を招き、納税事務の簡素化という簡易課税制度の持つ長所を損なうことから追加的な改正を行う必要はないのでではないか」との意見もありました。
さらに、平成14年11月の税制調査会の税制改革答申において「簡易課税制度はこれまで見直しが行われてきており、その適用割合は低下してきている。しかしながら、消費税制度が定着し事業者が納税事務に習熟してきたと考えられること、また、事務処理能力のある中小事業者の多くが損得を計算した上で適用している実態が認められる。こうしたことから、免税点制度の改正に伴い新たに課税事業者となる者の事務負担に配慮しつつ、簡易課税制度を原則廃止とすることが適当である。」としました。
このように税制調査会は一貫して、原則的にはすべての事業者に対して本則の計算方法による対応を求めるべきだとして、最終的には簡易課税制度を廃止するべきとの方針を打ち出しています。
簡易課税制度の業種区分とみなし仕入率
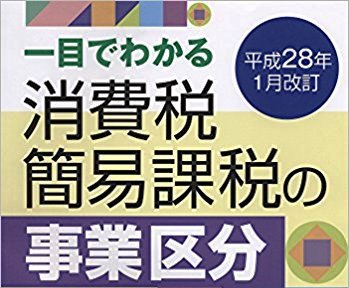
今後の簡易課税制度についての議論
H30年10月以後の税率アップ後の今後においても、消費税率の引き上げを伴う税制改正により、消費税制度は現行と大きく変わることが予想されます。
現行簡易課税制度は、「消費税制度の定着」及び「情報技術の発達による事務簡便化」という観点から、既にその立法時の目的(中小事業者の事務負担軽減)を達成していることに加え、「制度上の欠陥により発生する益税問題」があり課税の公平確保の上で看過できないとして、廃止すべきと主張する論者が多いです。
中小事業者における簡易課税制度の必要性
税制調査会は、消費税制度の制度が浸透し、簡易課税制度の役割は果たしたという見解です。しかし、中小事業者の事務は、未だ煩雑な消費税の本則計算を滞り無く行うことができる状態であるとは言い難いのが現状です。むしろ、期中の膨大な取引について処理するにあたり、その税額計算を間違うことなく処理できる方が少ないと考えられます。
たしかに昨今における会計ソフト等の情報技術の発達は目覚しいもので、高性能なものが安価な価格で入手できるようになり、この恩恵を享受する事業者は多いです。その一方、その恩恵に受けながらも未だそのソフトを使用する者の条件は、ある程度の専門的知識を必要とすることに変わりません。つまり、中小事業者の事務処理能力は、情報技術の発達に比例して効率化してはいないのが現実です。
具体的には、中小事業者が会計ソフト等を導入する際における設定は専門的知識を要し、さらに期中においても、取引ごとに税区分判定することが必要であり、一定程度の知識と経験がある者でないと過誤なく計算することは難しいです。これまで経験してきた会計事務所に出入りする中小事業者の様子を実感です。
このため専門事務員を雇用する余裕のない多くの中小事業者は、記帳代行を税理士に委託することが多いです。この場合でも、本則課税における仕入税額控除の集計は、仕入取引ごとに税区分(課税、非課税の区別等)を判定した結果を集計する為、手間がかかります。
これに比べ、簡易課税制度の採用を選択した事業主の消費税計算の多くは課税売上高を把握するのみで年間消費税の納付額を計算することが可能です。そこで記帳代行を主に取り扱っている税理士であっても、本則課税を選択した事業主に対しては、通常その手間分の顧問料を上乗せせざるを得ません。要するに、税理士に委託して本則課税計算の手間を省こうとすれば、事業主の経済的な負担が増してしまう実情があります。
あるべき業種区分とみなし仕入率の設定による益税の解消
現行の簡易消費税制度の実態は、前に述べたように総務省調査による日本標準産業分類をベースとして事業を区分され、その区分されている仕入れ率により税額計算を行う。この元々の区分とみなし仕入れ率について見直すことで、簡易課税制度の批判の対象となる益税額の発生を押さえることができます。
たとえば益税の発生は、実態よりも低いみなし仕入れ率を設定し、簡易課税を選択する者を損税とすることで完全に排除することが可能です。しかし、制度構築の段階から損税を認識したうえで、みなし仕入れ率を設定することには問題があります。制度論としては、納税者にも課税庁側にも中立な制度を構築しなければなりません。
益税の発生を現実的に押さえるには、総務省管轄の日本標準産業分類による事業区分を見習いつつ、ドイツにおける事業区分の見直しのように3年から5年ごとに財務省管轄による独自の定期的な実態調査を行い、遂次、事業区分を見直す手続きを、法制化するべきなのではないでしょうか。
今後の消費税法改正による簡易課税制度の方向性
税率の変更による複数税率制度の導入の影響について検討
H31年10月より、現行の8%から10%までに引上げられ、逆進性が加速することについて勘案された結果、複数税率の導入が決定されました。この複数税率の導入により、消費税制度はさらに複雑化し、これに加え実務上の事務処理の煩雑が増大されることが予想されます。複数税率の導入によりその税率の振り分けは事業者にとっても課税庁にとっても煩雑となり、かつ両者間の見解の相違が生じる原因となる為です。
現在における年間課税売上5,000万以下の課税事業者が選択適用できる簡易課税制度は、単一税率であることを前提としている。複数税率になれば、「売上に占める仕入割合」の考慮のみならず、「仕入における軽減税率適用品目の割合」をも考慮しなければならず、現行簡易課税制度における6つの仕入率により振り分ける制度では不十分です。そうなると、ドイツが採用しているように相当数の業種に分類する必要が生じます。
消費税制度の抜本的な改革
複数税率制度を成立させるためのインボイスの導入については、慎重論を踏まえ、事業者に極力負担感や手間を感じない書式とする必要です。EUにおいては新規の書類を導入した訳ではなく、長い商習慣の中で使われた書式を消費課税制度に組み込んだのであり、日本においても現在用いられている形式に若干改良を加えた書式を用いることが望ましい。そして、その前提として、活用が我国では遅れている「マイナンバ-制度」についても考慮しなければなりません。
納税義務者である事業者が正しく円滑に申告納税を行うために、滞納や益税が発生しない制度の見直しが必要です。中小事業者に対する措置は、国際的にみて高いとされる免税点1,000万円を低くする措置よりも、免税事業者に該当する事業者も本則課税を選択するような、申告納税制度の簡素化と電子化の促進を図ることで納税者と課税当局双方の事務を効率化すべきです。
現行の本則課税方式により算定される仕入税額控除額は、インボイス方式のように実際に課税されている消費税額を集計することで算定するものではなく、取引の相手方が、免税事業者であるかに関係なく仕入税額控除額等に算入される、「帳簿および請求書等保存方式」により消費税額を算定します。
昨今においては、中小事業者の財務諸表について、経営者にとって解りやすい(経営者目線の)勘定科目を設定することが多いです。消費税ソフトは通常、勘定科目ごとに税区分を初期設定時に設定します。
しかし、現行の帳簿を基準とした仕入税額控除の計算において、経営者目線の勘定科目の設定による消費税ソフトでは的確に対応し切れていないのが実務の現場です。これは、設定時と異なる税区分取引が発生すると手作業修正を行う必要が生じることによります。具体的には、たとえば税理士報酬(課税取引)を諸会費(通常、非課税取引と設定)とした場合等、経営者が管理しやすい簡素な勘定科目に統合した場合があります。現行制度では帳簿をもとに税額が計算されているため、この例示のような場合には、消費税ソフトによる機械的な経理処理に対して、税務上の修正を加えなければなりません。こうした事情が消費税額の計算の複雑化を招き、本則課税による消費税額の算定を難解なものとしています。この問題については、EU諸国の付加価値税にかかるインボイス制度を導入し、通常の法人税の計算と別個に切り離した計算制度にすると、消費税額の計算が実額の合計額から算定されることとなる為、計算を単純化させることで解決できます。

